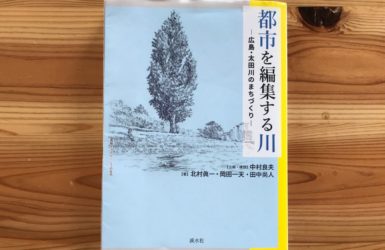2025.02.27
若者たちが親しめる水辺に。小さく改善し続ける福山市「芦田川かわまち広場」の現状と課題を見てきた

2020年3月、広島県福山市の中心部を流れる一級河川芦田川沿いに「芦田川かわまち広場(以下「かわまち広場」)が誕生しました。
隣接する市の体育館との連携を意識した作りになっており、フットサルやピクニック、バーベキューが楽しめ、そして全国的にもユニークなアクティビティとしてスケートボードパークも作られています。
設備の完成以降も運営面での試行錯誤が続く現場で話を伺ってきました。
発端は水辺隣接の競馬場跡地の活用検討
かわまち広場が計画されたのは、福山市営競馬場跡地に隣接する川辺。競馬場があった時代は、芝生が敷かれただけの寂しい場所でした。

かわまち広場整備前の航空写真

かわまち広場施工前の写真
その競馬場は、収益悪化などの理由から2013年3月のレースを最後に廃止。
翌年には、「福山市営競馬場跡地利活用基本構想」が取りまとめられ、芦田川の河川空間と連携した緑豊かな多機能空間として一体的な土地利用を行う方針が定められました。
その後、広大な跡地のうち半分を活用し、2020年に新しい福山市総合体育館「エフピコアリーナふくやま」(以下体育館)が誕生しています。
「もともと、競馬場と道を挟んだところに老朽化した旧体育館があり、それを競馬場跡地に建て替えることになったのですが、この建て替えには周辺の地域住民からも大きな期待が寄せられていました。戦災復興の財源を生み出すために設けられた競馬場は、市民の生活・福祉の向上に一定の役割を果たしてきましたが、必ずしも地域住民に歓迎されていたわけではありません。このため、かつてのイメージを一新し、エリア価値を高めることが求められていました。実際、体育館やかわまち広場が整備され、周辺には新築マンションなども建ち始めるなど、明らかにまちのイメージは変わりました」
そう話すのは、福山市建設局都市部公園緑地課の藤井康男さんと谷口徹さん(記事のコメントはすべて藤井さんのもの)。

写真左:谷口徹さん、写真右:藤井康男さん
市の課題解決のために水辺を活用
実は、競馬場跡地活用の動きとは別に、以前から芦田川をまちづくりに活用しようとする草の根的な活動も行われていました。
2011年に市民有志が立ち上げた「芦活部」は、福山の歴史・文化と自然の魅力を生かし、地方への人材回帰を促すこととを目的として、河川空間活用に向けた勉強会や清掃活動、市民参加型のイベントを2012年から継続的に行ってきました。
全国的にも河川空間のオープン化が進められる中、「水辺を使おう」という気運が高まりつつあったタイミングとも重なったのです。
こうした中、2016年には行政からの呼びかけで、芦活部を含む多様な河川利用団体が河川空間の活用を考える懇話会が設けられました。
当初は具体的な場所は想定せず、アイデアを出し合うに留まっていましたが、この間に競馬場跡地の活用計画が具体化され、体育館と河川空間をつなぐ方針が示されたことから、この場所がかわまちづくりの候補地に。
そして、官民でかわまちづくり計画を取りまとめられることとなったのです。

芦活部で実施した水辺で乾杯
この水辺活用には、都市・地域経営課題の解決につなげる狙いがあります。福山市の課題のひとつに『市外へ出ていく若者が多い』という点が挙げられます。
大学に進学する高校3年生の約7割は市外に進学しており、そのうちの8割が「将来地元に戻りたいと思っていない(「わからない」を含む)というのです。
そして、その理由としては「希望する職種や就職先が少ない」だけでなく、「遊ぶ場所が少ない」「愛着をあまり感じない」「まちに賑わいや活気がない」といった意見も多く挙げられており、まちに楽しさを求める若い層の思いが読み取れます。
それならば、若い人たちが愛着を感じるような楽しい場所、活気が感じられる場所をみんなで作ろうーー。
そんな思いからかわまち広場は計画されたのです。
スケートボードパーク実現までのさまざまな困難
完成したかわまち広場は体育館と芦田川の間に広がる約2.1㏊の親水広場で、体育館2階のテラスから直接広場入口にアプローチできるように市道をまたぐ連絡歩道橋が作られており、一体的に開発されたことが分かります。
.jpeg)
かわまち広場整備後の全景
かわまち広場の利用者が体育館で休憩したり、体育館の利用者がかわまち広場のイベントに参加したりするなど、かわまち広場と体育館が連絡歩道橋で結ばれることにより相互の施設の利便性が飛躍的に高まっています。
かわまち広場入口から、イベント時などに観覧席として使われる階段護岸を下りて広場中心部へ。
中央にはフットサルコート(1面)を含む広い芝生広場があり、スケートボードパークはその下流側にあります。
当初は1,000㎡でしたが、人気が高く利用者の増加とともに手狭になったことから、すぐに初心者用のパークを増設。
現在は1,800㎡ほどの広さとなり、中国エリアのヘッドパークとして注目を集めているそうです。

若者たちが集まる日中のスケートボードパーク
「東京五輪以降のスケートボード人気に加え、スケートボードができる場所自体が少ないこともあって週末には非常によく使われています。利用には事前の登録が必要で、2025年2月時点の登録者数は1,600人を超えています。計画当時、国が管理する区間の河川敷で本格的なスケートボードパークを設置した事例がなかったため、前例がない中で治水安全上の様々な制約をクリアする必要があり、設計には苦労がありました」

例えば、多彩なセクション(コンクリート製の障害物)は、増水時になるべく川の流れを阻害することがないよう配置や構造を工夫されています。構造物の高さは1mまでとし、それを超える転落防止柵などは、増水時に取り外しが可能な構造となっています。
セクションの配置も、利用者のコース取りを念頭に置きつつ、河積阻害率(橋梁を設計する際の橋脚の総幅が川幅に対して占める割合のこと。5%以内に制限されている)を考慮して、18m以内(川幅360m×5%)に収まるように設計されています。
それ以外にも、洗掘や土砂の流出を防止するための措置として、堤防法尻(切土や盛土によって作られた人工的な斜面の下側の終点)からスケートボードパークの間はコンクリートで舗装されていたり、誤侵入や飛び出し防止を目的とした緑化ブロックや植栽が配置したり。
随所に治水上・利用上の配慮があり、実に細かく設計されていることが藤井さんの説明から分かりました。
すでに完成形に見えるスケートボードパークですが、今もなお、環境改善に向けた取り組みが進められています。
夏場の猛烈な暑さを凌げるよう、夜間も利用できるようにしてほしいという利用者の声を受け、前例がない河川敷への照明灯設置に向けて、国交省と協議しているところだそうです。
まさに「市民の声に応えて進化する広場」というわけです。整備後もさらなる環境改善に取り組む理由は、やはり行政課題の解決に繋がることが期待できるからだと言います。
「市街地では騒音などで迷惑がられるスケートボードも、ここでは芦田川の雄大な景色の下、誰にも迷惑がられることなく思い切り楽しむことができます。そしてそれがまちの魅力となってシビックプライドを育んだり、多様な人々の日常のコミュニケーションの場になっていくことも期待しています」
祭り、スポーツその他、多彩な活用が可能
スケートボードパークの下流側には土の広場があります。
これも、かわまち広場ならではの施設。
通常の公園では火の利用は禁止されていることが多いのですが、ここでは規制を緩和しており、郷土の火祭り「とんど祭」が地元住民により毎年、開催されています。
芝生広場の上流側には石畳広場、バーベキューテラスがあり、さらに上流側は駐車場になっています。
石畳広場は車の乗り入れも可能で、イベント時にはステージを設置したり、展示、販売もできるフレキシブルなエリアとなっており、今後の賑わいづくりには欠かせない場になりそうです(営利目的で使用する場合や独占的に使用する場合は使用料が必要) 。
橋の近くに位置するバーベキューテラスは、あえて無料で自由に利用できる仕組みとしています。
これは、いわば公園の「お花見」と同じ考えで、行政が使用許可手続きにより厳格に管理するより、利用者のマナーとコミュニケーションに委ねた方が、管理者・利用者双方にとって負担が少なく、快適に利用できるのではないかとの考えによるものです。
供用開始以降、時折、小さなトラブルはあるものの、譲り合っての利用を呼び掛けていることから大きな問題は生じていないそうです。
開放的な河川敷でのバーベキューは楽しそうです。

バーベキューテラス
こうした広場と河川の間には、市が管理する幅員4mの自転車歩行者用通路と国が管理する幅員3mの河川管理用通路が約3kmにわたり整備されています。
それぞれウォーキングやマラソン大会、トライアスロンのコースとして利用できるようにつくられており、歩行者と自転車を分離するための路面標示(ブルーライン)や500m間隔での距離標示などが設けられています。
市民団体が企画運営する福山あしだがわマラソン、ふくやま夕焼けマラソン、福山かわまちトライアスロンなどのコースとして定着しており、年間を通じて何度も利用されています。
因みにこの区間は、福山駅から鞆の浦を経由して尾道につながる「しおまち海道サイクリングロード」のルートの一部としても位置付けられており、国が指定するNCR(ナショナルサイクルルート)の認定を目指しているそうです。

左側は河川管理用の道路、右側は市が整備した自転車歩行者用の道路
「日常的にこの道を散歩したり、ジョギングする方がかなり増えました。この道を通じて水辺の気持ち良さに気づいた方も多いでしょう。高齢者の健康寿命を延ばすことにも少なからず貢献しているものと思います。利用者にはスケートボードで走行しないこと、自転車で走る際にはスピードを出し過ぎないこと、管理用の道では管理用車両に注意することなどを意識していただきたいので、路面には注意喚起の標示もしてあります」
親水施設は整備されたものの、水辺の活用はまだこれから
水際は親水護岸として整備されており、場所によって構造が異なります。
けん引車両からボートを降ろすためのスロープ式の護岸もあれば、ボートを接岸させる喫水(船底から水面までの深さ)を確保した護岸、水際までステップになっている階段状の護岸、緩やかな勾配の捨て石が置かれている自然護岸など、水辺や水面でのさまざまな利用を想定して作られています。
ただ、残念なのは、どの部分も2025年2月時点では殆ど使われていないこと。
ボートが接岸できる護岸の前には、安全面を考慮した対策として転落防止柵が設置されており、取り外し可能チェーンが掛けられているためか、貸し出し用に準備したSUPボードの貸し出しも行われていません。
せっかく水辺に親しめるように作られているのに、現時点では必ずしも有効に活用されていないというのです。
「水上アクティビティのために作られた親水設備ですが、親水空間には水難事故の危険性も潜んでいます。利便性や快適性は万全の安全対策があってのこと。親水設備に限らず設計段階では色々と工夫を凝らしたつもりですが、実際の運用にはまだまだ課題があると考えています。引き続き、体験イベントなどの試行的な運用を重ねる中で、実装に向けて一つひとつ課題をクリアしていきたいです」

かわまち広場でのSUP体験の様子
「整備終了」から始まる、アップデートし続けるまちづくり
オープン当時の失敗談として、藤井さんは当初、「千代田地区かわまちづくり計画」の登録認定を受けた時点で営業活動を含むイベントの開催など、ソフト面の規制緩和も受けられるものと考えていたそうです。
しかし、供用開始後、河川敷地占用許可準則(以下「準則」)の都市・地域再生等利用区域の指定を受ける必要がある(準則第二十二)ことを国交省から知らされ、慌てて指定手続きを行ったそうです。
「区域指定を受けるには地域住民の合意が必要になります。出だしでつまずいたところがありますが、官民連携で公園の管理運営に取り組むきっかけになるのではと考えました。2021年6月に官民対話の場として「千代田地区かわまちづくり官民連携プラットフォーム(以下「プラットフォーム」)を設けました。プラットフォームは区域指定に向けた実証実験の実施主体とし、地域住民の合意形成を図る場とするとともに、その後も官民連携で広場の管理運営を行うための枠組として活用しています」
同プラットフォームには、河川管理者である国交省、公園管理者である福山市公園緑地課、隣接する体育館の管理者である福山市スポーツ振興課、指定管理者である福山市スポーツ協会に地元の自治会連合会、芦活部をはじめとする市民団体や民間事業者、学識経験者などが参加。
営業活動を含むイベントについては、原則としてプラットフォームの承認が必要とするルールとしています。
河川法上の占用主体を福山市としつつ(準則第二十二第4項第1号)、営業活動を行う施設使用者はプラットフォームとし(準則第二十五)、各イベントの主催者はプラットフォームの一員、という位置づけで整理されています。
プラットフォームでは、初年度を区域指定に向けた実証実験の期間と位置づけ、公募により様々なイベントを誘致し、試行的に実施することとしました。
その結果、2022年2月には、都市・地域再生等利用区域の指定を受け、晴れて営業活動を含む運営ができるようになったのです。
プラットフォームでの実証実験を通じて、供用開始後の利用状況やニーズ、課題等を共有する中で、官民の信頼関係が構築されたことにより、更なる環境改善に向けた取組について、それぞれ対等な立場で主体的に考えるようにもなりました。
プラットフォーム事業の公募はその後も継続して行っており、これまでにオーガニックマルシェやキッズヨガ、トライアスロン大会、スケートボード教室、音楽フェスなどの多彩なイベントが定着しています。
アーバンキャンプや仮装マラソン、ナイトシアターなど、ユニークなアクティビティも毎年誕生しているそうです。

スケボー教室


トライアスロン大会

River Side Fes

オーガニックマルシェ

ねそべリングシアター

スケボーショップ常設に向けた実験
一方、実証実験の結果、期待通りの成果が得られないこともありました。
スケートボードのマナー改善を目的に行ったトライアルサウンディングでは、仮設店舗でスケートボードショップの常設の可能性を探りましたが、採算確保が困難なことが分かりました。
それでも藤井さんは、試行錯誤のプロセスにこそ意味があるとして、アジャイル開発の姿勢で今後の展望を語ります。
「まずは仮説を立てて試行する。実際にやってみて課題を抽出し、それを元に次の手を考える。この繰り返しをスピード感を持って行うよう意識しています。スピード感を優先するあまり、周囲からは何をやっているのか理解されにくいこともあります。そもそも施設はすでに完成しているわけですから、従来の考え方だと行政の『つくる仕事』は終わっていることになります。しかし、かわまち広場では『つかいながらつくる』ことが重要だと考えているので、終わりはないのかもしれません。大きな目標としては、持続可能な管理運営に向けて、多様な主体によるパークマネジメントを実装できる形に近づけたいと考えています」
実現にはいくつかの障壁もあるようですが、かわまち広場に対する期待の高さを感じる藤井さんは、さらなる活用に向けた気運の高まりに手応えを感じています。
「様々な都市経営課題を解決するために水辺を活用するんだということを丁寧に伝えられれば、きっと共感が生まれ関係人口ももっと増えていくと思っています。そのためには、官民が共有できる分かりやすいビジョンが必要だと感じています。幸い、かわまち広場自体は広く認知されるようになってきました。まだまだ課題もありますが、変化に対する期待の声もいただきます。官民連携による水辺の活用を通じて公共空間を少しずつ変えていきたいと考えています」
福山市では水辺以外にも福山市中央公園や春日池公園などの再編に取り組んでおり、中央公園はすでにPark-PFIの仕組みを利用して日常的なにぎわいが生まれています。
こうしたまちの変化が福山市の若者たちにどう響くか。
そしてかわまち広場はどう変わり続けるのか。これからに期待したいところです。
この記事を書いた人
住まいと街の解説者。(株)東京情報堂代表取締役。オールアバウト「住みやすい街選び(首都圏)」ガイド。30数年不動産を中心にした編集業務に携わり、近年は地盤、行政サービス、空き家、まちづくりその他まちをテーマにした取材、原稿が多い。主な著書に「この街に住んではいけない」(マガジンハウス)「解決!空き家問題」(ちくま新書)等。宅地建物取引士、行政書士有資格者。日本地理学会、日本地形学連合、東京スリバチ学会会員。
過去の記事